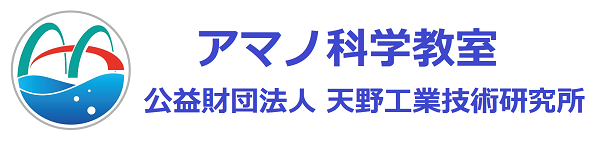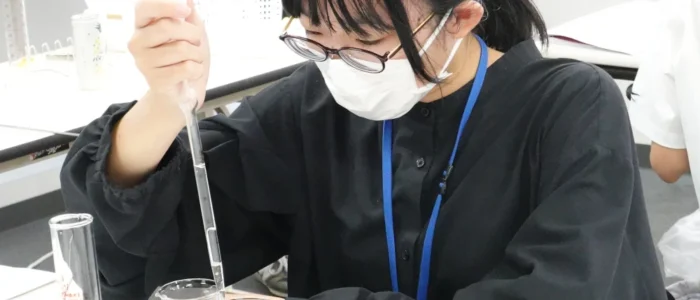Ⅱ 身体は、何でできているのだろう?
2 「水」の化学
1 水の不思議実験
2 軟水と硬水について
3 身体の中の水
からだを作っているいろいろな物質について、化学の眼で探究しています。前回の講座では、タンパク質や脂質、ミネラルについて実験を行いながら、その性質について学びました。
今回は水です。水は人間の生命を維持するうえでなくてはならない物質です。その不思議について学びました。
最初の実験です。おもりをつけた針金を氷にのせ、様子を観察します。どうなるでしょうか?


不思議なことに、針金は下がり、針金の通った後は氷はくっついて一つの氷になっています。まるで針金が氷を通り抜けていくようです。

どうしてでしょう?…それは、氷より水のほうが、密度が大きく、氷に圧力がかかると融点が下がるためです。
針金があたり、氷に圧力がかかる→氷は小さくなろうとする→水になり針金は下がっていく
針金が通過し、氷に圧力がかからなくなる→温度が0℃以下のため氷に戻る
この不思議な性質は水の水素結合に関係しています。スケートもこの現象を使っていますね。
2つ目の実験は、缶が一瞬でぺちゃんこになる実験です!!
アルミ缶に水を5mL入れ、コンロでアルミ缶を加熱し、湯気が出始めてから、20秒ほど加熱を続け、トングでアルミ缶をつかんで、アルミ缶の開いた口を下にして、水の中に一気に入れます。音にびっくりしますが、アルミ缶は見事につぶれました…なぜ?
原因は「水の三態と大気圧」、缶の中には最初は、水と空気が入っていましたが、加熱することで水は気体 (水蒸気)に変わり空気を追い出します。これを急冷すると、水蒸気が水に戻り缶内の圧力が減り、大気圧によって缶がつぶれてしまう!!という現象がおきていました。なんと、水が水蒸気になると体積は1200倍以上に、逆に水蒸気が冷やされて水に戻ると体積は1200分の1以下に。物質は、温度や圧力により、その状態を変化させます。これを状態変化といいます。例えば、水の場合、固体は氷、液体は水、気体は水蒸気。物質の三態といいます。


次の実験は、モルについての復習やメスシリンダー等の使い方の練習を兼ねて、水を採取し、モル数と水分子の個数を計算しました。5mL駒込ピペットで水を3mL、100mLメスシリンダーで水を50mLそれぞれ100mLビーカーに採取し、質量を量ってモル数、分子数を計算しました。


次の実験は、水の硬度と液性の測定です。精製水、水道水、日本の天然水(ミネラルウォーター)、フランスの天然水(ミネラルウォーター)を用意しました。硬度を試験紙で液性をBTB試薬で測りました。


フランスのミネラルウォーターは超硬水(ラベルには1468ppmと記載)、日本の天然水は軟水(硬度約30)。水1L中に含まれるカルシウムとマグネシウムを炭酸カルシウムの量に換算したもので、WHOの基準では、120mg/L以下が軟水、120mg/L以上が硬水とされています。日本の水はほとんどが軟水で、日本の地形や地質に由来していることを学びました。日本の天然水はほぼ中性、フランスの天然水はアルカリ性でした。


水に溶けている金属を調べるため、炎色反応を実験しました。スポーツドリンク、ミネラルウォーター、ミョウバンを溶かした水、ホウ酸を溶かした水をニクロム線につけて、コンロの炎の中へ、スポーツドリンクはナトリウムの炎色反応で強く黄色に発光、ホウ酸は明るい緑色でした。花火の色はこの炎色反応が使われています。


炎色反応がおこるのは、電子遷移によるものです。以前の講座で、電子配置について学習しましたね。熱によって電子が別の軌道に励起し、元の軌道に戻るときに放出する光が炎色反応です。
最後に、身体の中の水について考えました。水は体重の約何%かな?赤ちゃんは体重の約75%、子どもは約70%、成人は約60~65%、老人は50~55%が水だと言われています。体内の水の増減は、筋肉や脂肪に関係しています。筋肉の80%は水分で、脂肪の水分は20%だけだそうです。成長とともに体に脂肪がつき、老人になると筋肉の量が減ってくることが水の割合の変化につながっていると考えられます。
水の役割は?血液としての役割(血液の約55%を構成する血しょうは、約90%が水分)。体温調節の役割(運動をしたときに汗をかくのは、体温上昇を調節するため)。腎臓や尿との関係(老廃物の排せつや体内の水分量の調節も行う)。筋肉に対する役割(筋肉の成長を促し老廃物を排泄する)。水は人間はもちろんのこと、生き物にとってなくてはならないものです。今回の化学講座では水について考えてきました。事前の課題ではいろいろな感想や疑問が寄せられました。